そもそも時効とは
時効は、一定の事実関係が継続した場合に、その事実関係に沿った権利を認める制度です。
ある人が、所有者であるという事実関係が継続していれば、その所有者であるという事実関係に沿って、その所有者に所有権を認めます。
取得時効 権利者であるという事実関係が継続した場合に、その者に権利を認める制度を取得時効という。
消滅時効 ある権利が存在しないという事実関係が継続した場合に、その者の権利が消滅する制度
時効の効果
時効の効果は、起算日にさかのぼる(民法144条)。時効期間中に生じたさまざまな事実により煩雑な問題が生じないように、時効の効果は起算日にさかのぼるとされています。
例えば、借金が時効消滅する場合、時効期間中の利息や遅延損害金を支払う必要がなくなります。
時効の根拠
時効取得が成立すれば、例えば、もとの所有者は所有権を失うことになります。また、消滅時効が成立すれば、債権者は債権の行使ができなくなります。
時効制度により、公に権利の喪失が正当化されることになる。しかし、なぜ、このような重大な不利益が正当化されるのか。
⑴ 事実状態の尊重 長期間持続した事実状態を改めて変更する不利益と、その継続した事実状態をさらに継続していくという利益を、比較して、その継続した事実状態の継続の利益を優先するという趣旨である。継続した事実状態を前提として、第三者の権利関係が生じていた場合に、その継続した事実状態を覆してしまうと、第三者利益を害してしまうからである。
⑵ 権利の上に眠るものを保護しない 真実とはことなる事実状態を放置した者が不利益を受けてもやむをえないとの考え方である。
⑶ 立証困難の救済 一定の事実状態が長期間経過していると、通常はその事実状態が継続していることが真実であるとの可能性が高まる。そして、時間の経過とともに、その事実状態の真実性を証明する証拠資料は、失われていく。そこで、長期間継続した事実状態について証明の立証を救済する趣旨で、時効制度が設けられたというものである。
取得時効
取得時効は、一定の事実状態を継続した者に対し、権利を取得を認める制度である。
時効取得の対象は、所有権(民法162条)と所有権以外の財産権(民法163条)である。
取得時効の要件
占有 物を所持するということです。自分で直接占有するだけでなく、他人に占有してもらってもかまいません。
所有の意思 占有は、所有の意思をもって占有でなかればならない。所有の意思とは、物を排他的に支配する意思である。所有の意思があるか否かは、客観的に判断される。賃貸しているなど、他主占有では、いくら事実状態が継続しても、時効取得は成立しない。
平穏かつ公然 平穏とは、占有が暴力や脅迫によってなされたものでないことをいう。
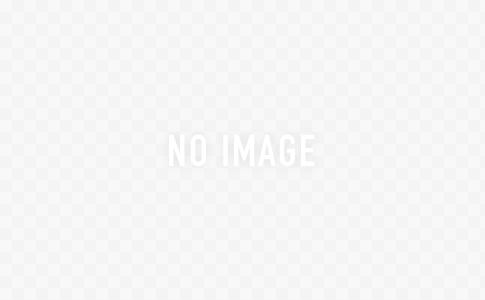
コメントを残す